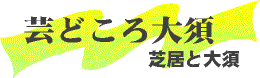
<出典 大須商店街連盟発行 大須より>
大須と芝居を語るとき、七代目尾張藩主宗春をはずしては語れない。この宗春は、質実剛健をモットーとする尾張藩主の中では異端的な存在で、生まれつき自由奔放な性格のうえにしゃれ者であった。町内見回りに白牛にまたがり、唐人笠をかぶり黒づくめの服装で現れ、みんなをびっくりさせた、なんてエピソードには枚挙にいとまがない。
そんな派手好きで浮かれ調子の宗春は、芝居見物も楽しみのひとつとして、大須界わいに芝居小屋をどんどんつくらせた。享保16年(1730)以降のことだ。それまでに大須に芝居小屋がたったのは二代目藩主が町の繁栄を願って寛文4年(1664)にあるが、三代目藩主が延宝6年(1674)に女形を禁止し、次第に芝居もすたれてしまった。この時点ではまだまだ庶民の娯楽として芝居は定着せず、小屋の数も少なかった。それが宗春の時代に入って大乗院、清寿院、大泉寺などの境内に十五、六もの小屋ができ、どの小屋もにぎわった。ただ芝居小屋といっても菰(こも)張りやよしず囲いで地面にむしろを敷いてみるお粗末なものだった。
これで大須に芝居が定着すれば大須の歴史も変わっただろうが、そうはうまくいかなかった。宗春の失脚後、元文3年(1738)から五年間にわたって上演中止の命が出されたのだ。寛保3年(1742)になり七ツ寺境内で歌舞伎狂言が再びはじまったというものの、道具立て「引き幕などはなく、木綿衣装なり」と当時の文献が記すように貧弱なもの。小屋も屋根葺きでないから雨天中止。しかし、それでも六年ぶりのなつかしさに七ツ寺はにぎわったようだ。
翌年では大須観音裏門でも興行がはじまったが、やはり宗春時代とは比べものにならない道具、建物であった。役者たちの生活も楽ではなくシーズンオフには大須観音や京都で大道芸人もどきのことをして生計をたてていたという。
ところが文化、文政になって再び芝居ブームが到来した。文化元年(1804)に橘町裏と若宮にやぐら太鼓を構えた大芝居がかかり、2年には中村歌右衛門、3年には市川国蔵ら、売れっ子役者が相次いで顔をみせた。まず文政元年(1818)江戸の名優、尾上菊五郎が岩井条三郎一座と君で、「天笠徳兵衛噺」を上演、大ヒットをとばした。こうした芝居ブームは、幕末まで続き、万延元年(1860)から不振に陥る。
明治3年に再興の道を歩みだし、橘町裏に小屋が設けられた。小屋の名前はオーナーの中村歌之助にちなんで中村座(7年に橘座と改称した)。こけらおとしは「白浪五人男」だった。5年には若宮と清寿院にも小屋ができ、6年になって桑名町筋本重町に新守座が誕生している。このあと13年、真本座(18年に千歳座と改称した)。16年、宝生座がそれぞれたった。
ほかにも七ツ寺近くに歌舞伎座などが姿を現し、これで大須も芝居の町になった...と思われたが30年にできた御園座におされて、この大須界わいにあった芝居小屋は、いわゆる格下げとなった。たとえば歌舞伎座は、その名と違って壮士劇を上演するようになったのだ。
しかし庶民の町、大須の芝居小屋にとっては、それでもよかったようだ。御園座ができても劇場数が減るわけでもなく、逆にむしろ増え続け、出し物も剣劇、落語、講談などの庶民受けするものが多くなった。当時の芝居小屋と出し物をみると宝生座は小芝居、新守座、千歳座は壮士劇、七宝館は浪曲と諸芸、文長座は落語、講談、帝国座は演芸、黄花園は剣劇と漫才、赤門劇場は上方演芸。そして橘座は南伏見町へ移転し音羽座と改称し、壮士劇を中心に活動した。
 |
これらの劇場も戦災などで姿を消す憂き目にさらされ、戦後、名古屋唯一の寄席として知られた富士劇場も閉鎖された。「芸どころ名古屋」にポッカリと穴があいた寂しさを感じさせていたが、昭和40年、芸能評論家たちが中心になって寄席復活のムードを盛り上げる運動をはじめた。その結果、開場の運びとなったのが大須演芸場である。その演芸場も東西の落語家やコメディアンの協力に支えられながら、幾多の波を経て現在に至る。又年末には吉例 大須師走歌舞伎 、ロック歌舞伎 スーパー一座が公演される。 | |
| 大須演芸場 【ブロック】 ブロックA3 |
![]() ご意見、要望、情報のメールはshidashi@mxp.mesh.ne.jpまで
ご意見、要望、情報のメールはshidashi@mxp.mesh.ne.jpまで
